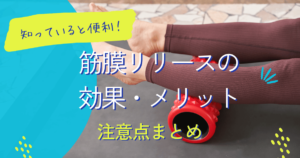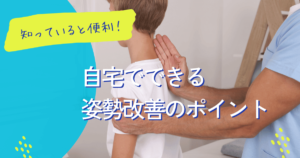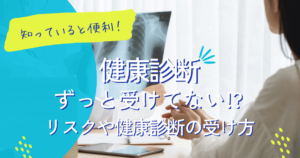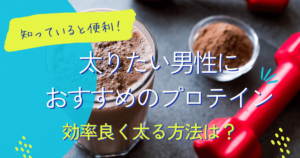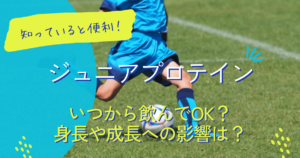本記事にはプロモーションが含まれている場合があります
耳鳴りの治し方・原因ごとの効果的な治し方を解説

突如として、聞こえてくる耳鳴り。
「悩ましい耳鳴りの原因って何なの?」と気になっている方も多いのではないでしょうか?
この記事では、耳鳴りの原因・メカニズム・対処法を紹介していきます。
是非、最後まで記事を読んで耳鳴りの改善に役立てて下さい。
耳鳴りの原因
耳鳴りの原因は、「聞こえにくさ」です。
耳鳴りを持っている人の大半は、「聞こえにくい」という悩みを抱えているといわれています。
通常、人間は20代後半から耳の老化が始まり、高い音が聞こえづらくなります。
脳が音を認識しづらくなると、音を認識すべく、異常に頑張ってしまうのです。
その結果、普段は気づかないような音までも拾ってしまうため、耳鳴りにつながりやすくなってしまいます。
そして、「聞こえにくさ」は耳の病気が原因になるものと、ストレスが原因のものとがあります。
次の章でそれぞれ紹介していきます。
耳の病気が原因の耳鳴り
耳の病気が原因の耳鳴りは4つあります。
- 突発性難聴
- メニエール病
- 聴神経腫瘍
- 中耳炎
突発性難聴
突発性難聴は、突然片側の耳だけ聞こえにくくなり、耳鳴りの他にめまいを伴うこともあります。
放置すると聴覚を失ってしまうことが多いので、早めに医療機関を受診することが必須です。
早期に治療をすることで、聴覚を失わずに済むことが多い点も特徴になります。
メニエール病
メニエール病は、突然ぐるぐる回るようなめまいが起きて、吐き気を伴うのが特徴です。
めまいの後に耳鳴りが起こります。
20〜50代の女性に多く発症し、耳の中にあるリンパ液が増えてしまうことが原因となります。
症状が辛かったり、改善しなかったりした場合は医療機関を受診してみてください。
聴神経腫瘍
聴神経腫瘍は、耳から脳につながる聴神経に良性の腫瘍ができてしまう病気になります。
腫瘍が小さいうちは無症状のことが多いです。
しかし、腫瘍が大きくなってしまった場合は聴神経を圧迫してしまいます。
聴神経が圧迫されることで耳鳴りが起こることがあります。
中耳炎
中耳炎は、細菌感染によって中耳に膿がたまることで、耳がつまった感じになり耳鳴りを起こします。
耳鳴りの他に、耳痛を伴うのが特徴です。
症状が進行すると、めまいや発熱を引き起こすこともあります。
ストレスが原因の耳鳴り
ストレスも耳鳴りを発症させる要因の1つとなり得ます。
人間関係や仕事などの精神的ストレス、過労や睡眠不足などの身体的ストレスで、自律神経が乱れることが原因です。
緊急性は低いですが、耳鳴りが長引く場合は、難聴に移行する可能性も。
耳鳴りがなかなか改善しない時には、医療機関の受診を検討しましょう。
以上、耳鳴りの原因を紹介しました。
では、症状によって耳鳴りのパターンに違いがあるの?と思われた方も多いのではないでしょうか?
次の章で、それぞれの耳鳴りのパターンにスポットを当てて紹介していきます。
耳鳴りのパターン
耳鳴りのパターンは「病気」の時と「ストレス」の時によって異なります。
耳の病気による耳鳴りのパターン
耳鳴りのパターンは2つあります。
「キーン」「ピー」など高音の耳鳴り
突発性難聴、聴神経腫瘍、メニエール病では、高音の耳鳴りがするのが特徴です。
内耳の異常に由来する場合は高音の耳鳴りとなって現れます。
「ブーン」「ザー」など低音の耳鳴り
中耳炎、メニエール病では、低音の耳鳴りが特徴です。
内耳の異常とは異なり、中耳の異常の場合は低音の耳鳴りとなって現れます。
前述でメニエール病は、高音の耳鳴りと紹介しましたが、人によっては低音で聞こえることもあるようです。
ストレスが原因の耳鳴りのパターン
ストレスでの耳鳴りのパターンは、「キーン」「ピー」と言う高音が特徴です。
突発性難聴などと同じ耳鳴りパターンですので、「ストレスだから」と決めつけずに一度、医療機関を受診してみてください。
受診が必要な危険な耳鳴りの症状
耳の病気によるものとストレスによる耳鳴りの症状を紹介してきましたが、中には危険な耳鳴りの症状もあるのが事実です。
命に直結する危険性もあるので、早めの受診が必要になります。
この章では、危険な耳鳴りの症状を紹介していきます。
「ドクドク」と言う心臓音のような耳鳴り
このような耳鳴りを自覚した場合は、脳梗塞や脳出血の前兆である可能性が高いです。
脳梗塞や脳出血を起こしやすい人は、全身の血管が狭くなっている傾向にあります。
狭くなった耳の周りの血管に血液が勢いよく流れることで、心臓音のような耳鳴りになります。
心音と連動して聞こえることが特徴です。
放置すると、脳梗塞や脳出血を起こし、麻痺や言語障害などの後遺症が残ります。
最悪の場合は死に至りますので注意が必要です。
心臓音のような耳鳴りがしたら、ただちに医療機関を受診しましょう。
耳鳴りの治し方
この章では、耳鳴りの治し方を紹介していきます。
耳鳴りの治し方は大きく分けて以下の3点に分類できます。
- 医療機関での治療
- 整骨院での治療
- 自分で対処する
それぞれについて詳しく解説しますので、ぜひチェックしてみてください。
医療機関での治療
医療機関での耳鳴りの治し方は4つありますので、それぞれ次の章で詳しく解説します。
- 薬物療法
- 音響療法
- 精神療法
- 手術療法
薬物療法
最も一般的な方法です。
神経細胞を修復させる薬と内耳と末梢神経の循環を改善させる薬が処方されることが多くあります。
その他、患者さんの状態に合わせて漢方薬や抗不安薬が処方されることも多いようです。
中耳炎で耳鳴りが起きている場合は、中耳に溜まった膿を出すために抗生物質が処方されます。
音響療法
自然音に近い音を聞かせて、脳に休息を促す方法です。
耳鳴りは認識できなくなった音を認識しようと脳が頑張っている状態になります。
定期的に音を流すことで、音を認識できるように働きかけます。
脳が無音状態ではないことを判断できるようになると、耳鳴りを軽減させることが可能です。
精神療法
耳鳴りに悩む患者さんの精神的ケアを行う方法です。
「病は気から」と言う言葉があるように、専門医の診察を受けることで患者さんが安心感を得られると、耳鳴りも少し軽減する場合があります。
症状の程度によっては、抗精神薬が処方される場合も。
手術療法
聴神経腫瘍による耳鳴りの場合は、腫瘍をとる必要があるため手術療法が取られます。
しかし、運動失調やふらつきなどの合併症が起こりやすく、難易度の高い手術です。
専門医でなければ行うことができません
整骨院での治療
耳鳴りは、整骨院でも治療が可能です。
整骨院での治療目的は、骨盤や背骨を矯正して自律神経を整えることになります。
骨盤や背骨は、自律神経が集まっている場所です。
矯正することで血流が改善されて自律神経が整います。その結果、耳鳴りの改善が目指せるのです。
紹介した方法は、病院や整骨院での治療法になりますが、病院での治療に抵抗があったり、病院へ行く程ではないと思われる方もいるかと思います。
次の章では、自分で対処できる方法を紹介していきます。
自分で対処できること
自律神経を整えることで耳鳴りが改善することもあります。
改善方法として、主に2つの方法があるので、それぞれ紹介していきます。
昼夜逆転の生活を避ける
朝に起きて夜は寝ると言う規則正しい生活リズムを心がけることで、自律神経のバランスが整いやすくなります。
人間の身体は、24時間リズムで機能するのが一般的です。
昼夜逆転の生活が続くと自律神経のバランスが乱れて、交感神経優位になってしまいます。
起床と同時にカーテンを開けて朝日を取り入れてみて下さい。
朝日を浴びることで夜に脳からメラトニンと言うホルモンが放出されて自然に入眠しやすくなります。
リラックスする時間を作る
リラックスする時間を作ることも自律神経を整えることに有効です。
ストレスで緊張状態の時は交感神経が優位ですが、リラックス状態は副交感神経を優位にさせます。
交感神経だけではなく、副交感神経優位の時間を作ってあげることで、両者のバランスがとれやすくなります。
その結果耳鳴りが改善する可能性もあるのだとか。
本を読む、音楽を聞くなどの時間を持って緊張状態を解き放つよう心掛けてみて下さい。
まとめ
この記事では、耳鳴りの原因、耳鳴りのパターン、耳鳴りの治し方、自分で対処できることなどを紹介してきました。
耳鳴りは、耳の病気が原因のこともあれば、ストレスによるもので起こることもあります。
自分での原因の究明は難しいことが多く、中には命にかかわる危険な耳鳴りもあるので、まずは専門医を受診することがおすすめです。
専門医の診察を受けた上で、自分に合った方法で耳鳴りの改善を目指してみて下さい。